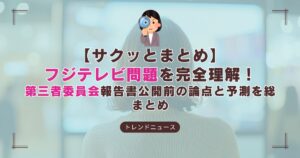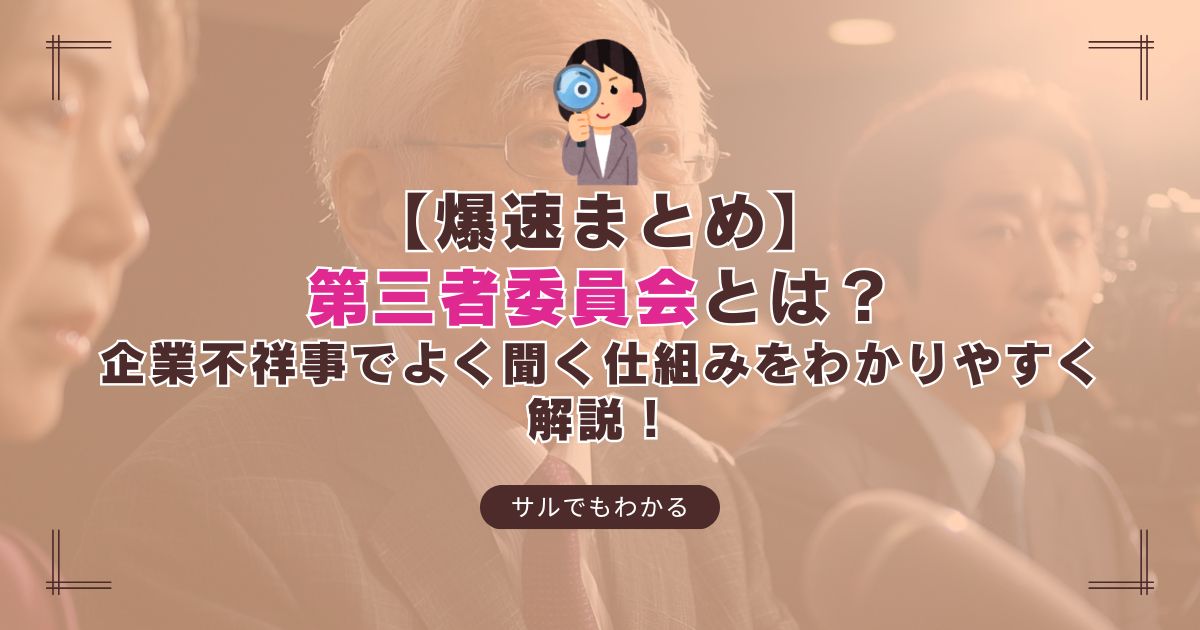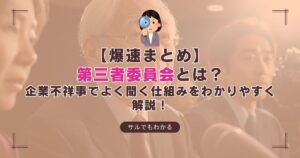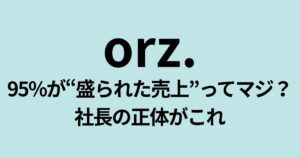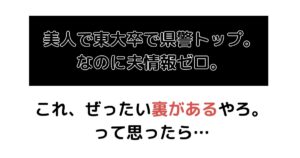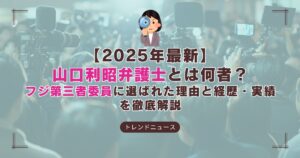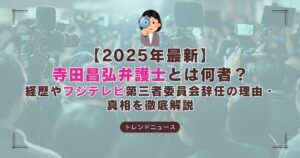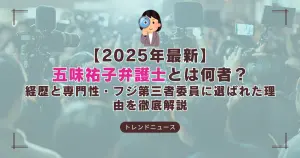ニュースで「第三者委員会」という言葉、 最近よく聞きますよね。
「第三者委員会って一体何をする組織なの?」 「本当に公正に調査できるの?」と疑問な方へ。
この記事では「第三者委員会とは」の定義、 内部調査との違い、設置目的をサクッと解説します。
第三者委員会とは?基本をやさしく解説
「第三者委員会」とは、企業から独立した外部の専門家が集まり、公正な調査をするための特別チームのこと。
難しく感じるかもしれませんが、かんたんに言えば「企業以外の人が客観的に調べるチーム」です。
定義:外部の専門家による独立した調査チーム
第三者委員会とは、企業の不祥事などを調べるため、外部から招かれた専門家の調査チームです。
企業の内部の人間ではないため、公平性が保てるんですね。

なるほど、企業とは関係ない専門家がやるから公平なのか!
設置の目的:何のために第三者委員会を置くのか
第三者委員会の目的は、大きく分けて3つあります。
- 不祥事の原因を明らかにすること
- 公平な調査で社会の信頼を取り戻すこと
- 同じ問題が二度と起きないように再発防止策を提案すること
第三者委員会を置くことで、「ちゃんと調べた」という信頼感が高まるんですね。
常設ではない“特別チーム”である
第三者委員会は、何か問題が起きたときだけ作られる臨時チームです。
「毎日何かを調べている常設チーム」ではありません。
たとえば、大きな不祥事が起きたときだけ、「よし、第三者委員会を立ち上げよう!」となるわけです。

あ、毎回常にいるわけじゃないんだね。問題が起きた時だけ呼ばれるのか。
ここまでで「第三者委員会とは」の基本が掴めましたね。
次のセクションでは「内部調査との違い」を解説しますね!
内部調査とどう違う?第三者委員会の特徴
「第三者委員会」と「内部調査」の大きな違いは、調査する人が企業内の人か外の人かという点です。
ここでは、それぞれの違いと第三者委員会の特徴を具体的に説明しますね。
内部調査委員会とは
「内部調査委員会」は、企業の社員が中心となって調査を行うチームです。
そのため、企業内の事情に詳しく、すばやく調査が進みます。
しかし、内部調査には次のようなデメリットがあります。
- 客観性が疑われる(会社に都合の悪いことを隠しがち)
- 社内の人間関係に左右されることがある
一方、第三者委員会はこれらのデメリットをカバーできます。
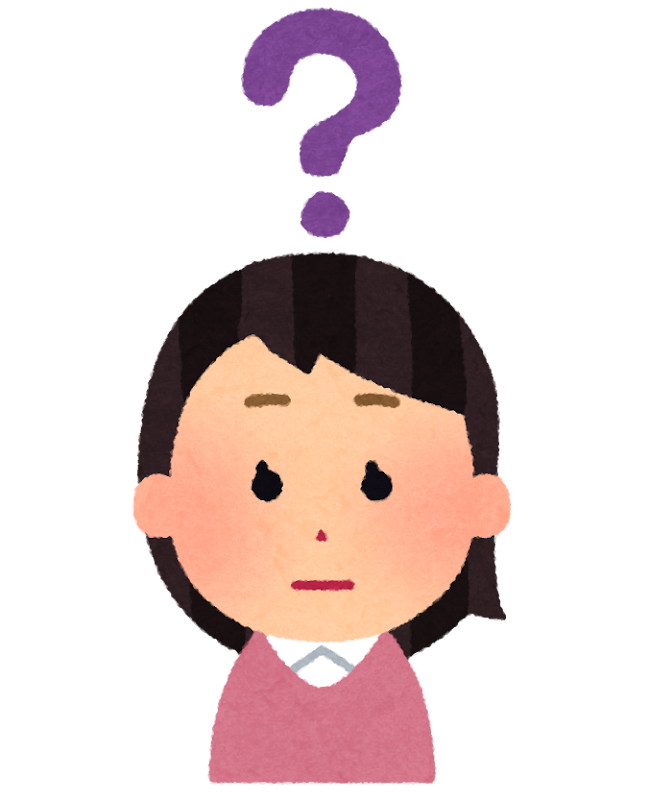
内部調査は社内の人だから、本当に公正な調査ができるか不安だな…
第三者委員会のメリット(長所)
第三者委員会のメリットは以下の3つです。
- 独立性・中立性が高い
- 会社と無関係の専門家が調査するので、信頼性が高い。
- 専門知識が豊富
- 弁護士や会計士など、専門家が調査するので調査の質が高い。
- 社会的な信用の回復につながる
- 公平で透明な調査により、世間からの信頼を取り戻しやすくなる。

外部の専門家なら信頼できそうだね!
第三者委員会のデメリット(短所)
一方、第三者委員会にもデメリットがあります。
具体的には以下の2つです。
- 時間がかかる
- 外部の人が調査するため、どうしても内部調査より時間がかかる
- 費用が高額になる
- 弁護士や専門家を雇うため、数百万円~数億円の費用が発生することも。
第三者委員会は公正ですが、コストや時間の面では企業の負担も大きいんです。

やっぱりコストが結構かかるんだ…でも信頼のためには必要なのかな?
ここまでで、第三者委員会と内部調査の違いや特徴が分かりましたね。
次のセクションでは、第三者委員会に「どんな人が選ばれるか」を詳しく見ていきます!
第三者委員会はどんな人で構成される?
第三者委員会は、企業と利害関係がない外部の専門家によって構成されます。
ここでは、具体的な委員の選び方や人数・規模について解説しますね。
委員の選任基準(誰が委員になる?)
第三者委員会の委員になるのは、基本的に企業とは利害関係のない人です。
よく選ばれるのは、以下のような人たちです。
- 弁護士
- 公認会計士
- 大学教授や研究者などの学識経験者
- ジャーナリストなど第三者視点を持つ専門家

なるほど、弁護士とか会計士ならしっかり調べてくれそうだね!
企業の顧問弁護士(いつも企業側についている弁護士)は選ばれません。
あくまで「完全に中立」な人を選ぶのがポイントですね。
人数や委員会の規模
第三者委員会の人数は、原則として3人以上が一般的です。
大きな問題の場合は、さらに多くの委員が選ばれることもあります。
具体的な例を挙げると、最近ニュースで話題になった日本大学のケースでは…
- 弁護士14名
- 公認会計士3名
という大規模な調査チームが結成されました。
調査の規模は問題の大きさによって変わります。

大きな問題だと人数も多くなるんだね。意外としっかり調査するんだな…!
ここまでで、第三者委員会がどんなメンバーで構成されるのか分かりましたね。
次は、第三者委員会が設置される具体的なケースを紹介します!
第三者委員会はいつ・どんな場合に設置される?
第三者委員会は、主に企業や学校、行政機関などで重大な問題が起きたときに設置されます。
ここでは、具体的にどんなケースで設置されるかを見ていきましょう。
企業不祥事の場合
企業で大きな不祥事が起きた場合、第三者委員会が設置されることが多いです。
たとえば、以下のようなケースですね。
- 粉飾決算やデータ改ざんが発覚したとき
- パワハラやセクハラなどのハラスメント問題
- 製品の品質偽装やリコール問題
最近の例で有名なのは、ビッグモーターの保険金不正請求問題。
第三者委員会が入ってしっかり調査したことで、大きなニュースになりました。

ニュースでよく聞くあの事件も、第三者委員会が調べてたんだ…!
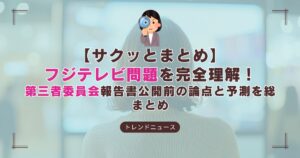
学校・行政の場合
第三者委員会は、企業だけではなく学校や行政でも設置されます。
たとえば、以下のような事例があります。
- 学校で重大ないじめ問題が起きたとき
- 自治体の不祥事が発覚したとき
学校の場合は「教育委員会がいじめ問題で第三者委員会を設置」とニュースで見かけますよね。
企業だけじゃなく、公共の問題を調べるときにも役立っているんです。
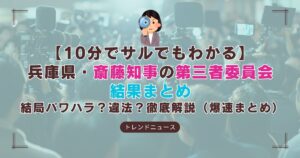
第三者委員会が必要と判断されるケース(ガイドラインより)
第三者委員会を設置すべきケースは、実は「ガイドライン」が定められています。
日弁連(日本弁護士連合会)が定めた基準では、以下のような場合が該当します。
- トップ(社長など)が不祥事に関与している可能性がある場合
- 問題が専門的すぎて、内部調査では限界がある場合
- 社内で隠蔽や情報操作の恐れがある場合
出典:日本弁護士連合会(https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100715_2.html)
つまり、企業内だけでは真実を明らかにしづらい状況のときに、第三者委員会が活躍するんですね。

トップが関与すると内部調査じゃ難しいもんね。だから外部の専門家が必要なのか…!
ここまで、第三者委員会が設置される具体的なケースが分かりましたね。
次は、第三者委員会がどんな手順で調査を進めるのかを解説します!
第三者委員会の進め方と調査の流れ
第三者委員会は、問題発覚から調査報告まで一定の流れで調査を進めます。
ここではその具体的な手順を、順を追って簡潔に紹介しますね。
設置の判断から委員会立ち上げ
第三者委員会は、企業内で問題が深刻だと判断された場合に設置されます。
流れを簡単にまとめると…
- 企業内で問題の深刻さを判断する
- 第三者委員会の設置を決定
- 外部の専門家に委員として参加を依頼する
- 委員が承諾し、正式に第三者委員会が発足
こういった流れで、第三者委員会が立ち上げられます。

問題が深刻になった時点で委員会を作るんだね!
調査の方法(ヒアリング・資料調査等)
第三者委員会の調査は主に以下の方法で行われます。
- 関係者へのヒアリング(聞き取り調査)
- 社内文書やデータの精査
- 必要に応じて現場検証
- パソコンなどの電子データ調査(フォレンジック調査)

専門的で本格的な調査をするんだな…さすがプロ!
第三者委員会は、企業から完全に独立しているため、調査が客観的に進みます。
調査期間
第三者委員会の調査は、ケースにもよりますが通常は数か月程度です。
大きな問題の場合、半年以上かかることも珍しくありません。
調査に時間がかかる理由として…
- 外部の人間なので企業内の事情把握に時間がかかる
- 多くの関係者へのヒアリングや資料確認が必要になる
こういった点が挙げられます。
調査報告書の作成と公表
第三者委員会は調査を終えると、必ず「調査報告書」を作成します。
この報告書は、原則的に公開されるものです。
報告書が公開される理由は、以下の通りです。
- 調査の透明性を確保するため
- 企業が隠蔽や改ざんをできないようにするため
- 社会的な信用を取り戻すため
企業はこの報告書を受けて、問題への対応を迫られることになります。

報告書は公開されるんだね。これなら企業もごまかせないね。
報告書提出後の対応(再発防止策へ)
調査報告書を受け取った企業は、その内容をもとに改善策を実行します。
- 不祥事の原因を取り除く
- 再発防止策を具体的に実施する
- 社内のルールを見直す
こうした対応を行うことで、ようやく企業の信頼回復が可能になります。

調査だけじゃなくて、問題を繰り返さないための改善もセットなんだね!
ここまで、第三者委員会の調査の流れを理解できましたね。
次は、「第三者委員会に関するよくある質問」にお答えします!
第三者委員会に関する素朴なQ&A
ここでは「第三者委員会」に関して、よくある疑問や不安に答えていきます。
素朴な疑問をすっきり解消しましょう!
本当に公平な調査なの?
結論から言うと、公平性はかなり高いです。
第三者委員会は企業とは無関係の外部専門家が担当します。
さらに「日弁連ガイドライン」というルールに基づき、公平な調査が行われる仕組みです。
最近では「第三者委員会報告書格付け委員会」というものもあり、報告書の公平性を評価しています。

公平さを保つためにガイドラインがあるんだね!
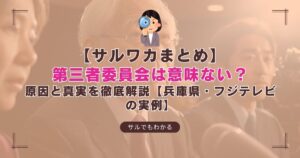
警察や裁判とはどう違うの?
第三者委員会と警察や裁判の違いを簡単に説明すると…
| 比較項目 | 第三者委員会 | 警察・裁判 |
|---|---|---|
| 強制力 | なし(企業の自主調査) | あり(捜査権・司法権) |
| 調査範囲 | 柔軟で広範囲 | 法律に基づく範囲のみ |
| 目的 | 原因究明と再発防止 | 犯罪の摘発や処罰 |
つまり、第三者委員会は「企業が自らを調査する」ための自主的な組織なんですね。
費用はどのくらい?企業にとって負担では?
第三者委員会の費用は、調査内容や規模で大きく変わります。
一般的な目安は以下の通りです。
- 小規模なケース:数百万円~数千万円
- 大規模なケース:数億円以上になることも
費用はすべて企業が負担します。
企業にとっては確かに大きな出費ですが、信頼回復のためには避けられないコストですね。

調査にはそんなにお金がかかるんだ!企業も大変だね…
報告書は全部公開されるの?
原則として報告書は公開されます。
個人情報やプライバシーに関する部分は伏せられますが、問題の核心部分は必ず公開されます。
理由は以下の通りです。
- 調査結果を隠さず透明にすることで信頼を回復するため
- 企業が隠蔽しないよう、社会から監視を受けるため
もし一部でも隠そうとすれば、かえって世間から批判を浴びることになるんですね。

全部公開されるなら安心だね。企業もごまかせない!
次は最後の「まとめ」に入ります!
まとめ – 第三者委員会を知ればニュースの見方が変わる
今回は「第三者委員会とは何か」をわかりやすく解説しました。
ポイントを簡単におさらいしましょう。
- 第三者委員会は企業から独立した専門家チーム。
- 公平で透明な調査により信頼回復を図る。
- 社内調査に比べ、独立性が高いがコストや時間がかかる。
- 報告書は原則として公開されるので、隠蔽は難しい。
第三者委員会が入ると、企業の不祥事対応も本気度が増します。
今後ニュースで「第三者委員会が設置された」と聞いたら、ぜひ注目してみてくださいね!
また、このブログでは実際の第三者委員会の事例も詳しく紹介しています。
興味があればぜひ他の記事もチェックしてみてください!